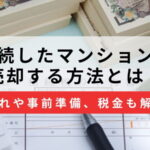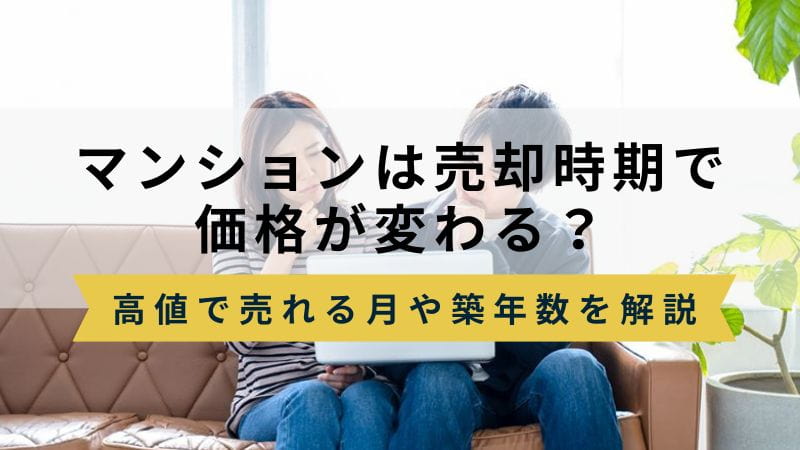
マンションは売却する時期で価格が変わる?高値で売れる月や築年数を徹底解説
マンションの売却価格や成約スピードは、売り出す時期によって大きく変わります。
マンション売却に適した時期や高値で売れるポイントをわかりやすく解説。
さらに、築年数ごとに売却するときのコツを具体的に紹介しています。マンション売却で適切な判断ができるようになりたい方は、最後までご覧ください。
マンション売却しやすい月(季節)はいつ?
マンションの売却は、時期によって売却価格や売却のスピードに大きな差がでます。
特に不動産市場は季節の影響を受けやすいため、適切なタイミングを見極めることが大切です。
東日本不動産流通機構がまとめた「レインデータライブラリー」の中古マンションの成約件数を踏まえながら、売却に適した時期を解説します。
1月~3月
1月〜3月にかけては、転勤や進学による引っ越し需要が高まります。
新年度に向けた住宅探しが活発化し、マンション購入希望者の意欲も高まるため、売却がスムーズに進む傾向です。
また、立地などの条件が良いマンションであれば、希望する価格での売却も期待できます。
東日本不動産流通機構がまとめたデータによると、2024年1月〜3月の成約件数の合計は9,871件です。
この件数は年間の26.5%を占めており、それなりに高い数値といえるでしょう(※表1参照)。
10月~12月
10〜12月は、新年に向けて新居での生活をスタートさせたい方が多く、1〜3月に次いでマンション購入の意欲が高まる月です。
東日本不動産流通機構のデータでは、2024年10月〜12月の成約件数の合計は9,457件で、年間の25.4%を占めています。
この時期は、年末までに新居を確保したい買主や翌春の転勤に備えた早期購入者の動きが活発です。
そのため、年末までに売却を完了してしまいたい場合におすすめの時期です。
マンション売却が難しい月
売り急ぐ事情がないのであれば、以下の時期を避けて、次の需要の時期を待つのも一つの方法です。
ここでは、マンション売却が難しい時期について解説していきます。
7〜9月
夏場は夏季休暇や猛暑の影響で内覧希望者が減少し、不動産市場全体が低迷しがちです。
東日本不動産流通機構のデータでも、2024年7〜9月の成約件数の合計は8,539件と少なく、年間の22.9%で平均を下回ります。
また、公益財団法人不動産流通推進センターが公表している「不動産市況データ」では、2024年7月の成約件数は前年比で減少しています。
7〜9月の時期に売却を急ぐ場合は、売却しやすい価格に調整したり、内覧に来やすい工夫(エアコンの効いた室内に案内するなど)を行ったりするとよいでしょう。
4〜6月
新生活が始まって以降の時期は、多くの家庭が引っ越しを完了しており、売却需要が一時的に減少する可能性が高いからです。
東日本不動産流通機構のデータでは、2024年4〜6月の成約件数の合計は9,355件で、年間の25.1%にとどまっています。
また、公益財団法人不動産流通推進センターのデータでも、2024年度の既存マンションの物件成約数は、全国的に4月と5月に落ち込んでいます。
表1:首都圏の中古マンション 2022 年〜2024年 成約件数一覧※REINS
| 1〜3月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 合計 | |
| 2022年 | 9,311 | 8,974 | 8,440 | 8,704 | 35,429 |
| 2023年 | 9,263 | 8,802 | 8,794 | 9,128 | 35,987 |
| 2024年 | 9,871 | 9,355 | 8,539 | 9,457 | 37,222 |
参考資料:
REINS | 季報 Market Watch サマリーレポート <2024 年 7~9 月期>
REINS | 月例速報 Market Watch サマリーレポート <2024 年 12 月度>
公益財団法人不動産流通推進センター | 指定流通機構の物件動向について(令和6年12月)
マンション売却をしやすい築年数はいつ?
中古マンションの築年数は売却価格に大きく影響します。
2023年に東日本不動産流通機構がまとめたデータによると、中古マンションの㎡あたりの単価は、築0〜5年で112.55万円に対し、築41年以上の場合は46.37万円です(表2参照)。
以下に、築年数ごとの特徴と売却ポイントをまとめました。
表2:築年数からみた中古マンションの成約状況(2023年)
| 築年数 | 成約価格
(万円) |
面積
(㎡) |
㎡あたりの単価
(万円/㎡) |
| 築0〜5年 | 7,077 | 62.87 | 112.55 |
| 築6〜10年 | 6,655 | 66.19 | 100.54 |
| 築11〜15年 | 5,932 | 68.19 | 86.99 |
| 築16〜20年 | 5,509 | 70.49 | 78.15 |
| 築21〜25年 | 4,887 | 70.60 | 69.23 |
| 築26〜30年 | 3,344 | 64.94 | 51.48 |
| 築31〜35年 | 2,303 | 57.66 | 39.94 |
| 築36〜40年 | 2,672 | 57.63 | 50.49 |
| 築41年〜 | 2,260 | 56.00 | 46.37 |
参考資料:REINS | REINS TOPIC 築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年) マンション成約物件、築40年超の比率は全体の18%
築5年未満
表2から、築5年未満の中古マンションは需要が高いことがわかります。
設備の新しさや内装の美しさは買主にとって魅力的に感じるでしょう。
ただし、価額が高額になると買主の住宅ローンが通りにくく、売却が成立しないといった問題も生じがちです。
また、マンション所有期間が5年未満の場合、短期譲渡所得となるため税率が高くなります。
税金面で優遇を受けるのであれば、物件の所有期間が5年を超えるタイミングまで待つのも手です。
ローン残高が多い場合は、ローン残高が物件の売却額を上回る「オーバーローン」状態になります。
ローンが残っている状態なので、仮に新しい物件を購入した場合は、月々の返済額が増えてしまいます。
マンションを売却するにあたって、オーバーローンのリスクを十分に検討することが重要です。
築6~10年
築6〜10年の場合、マンションの内装に大きな劣化はみられません。
そのため、新築のようなマンションを安く購入できることは、買主へのアピールになります。
マンションの所有期間が5年を超えると長期譲渡所得になり、税率が低くなることもメリットです。
また、この時期では修繕積立金の支払いが少なく済む点も、買主にとっての安心材料です。
2023年に東日本不動産流通機構がまとめたデータによると、築6〜10年の中古マンションの成約件数は全体の13.6%を占め、需要があることがわかります(表3参照)。
表3:中古マンション 築年帯別構成比率(2023年)
| 築年数 | 成約率
(%) |
新規登録
(%) |
対新規登録成約率(%) |
| 築0〜5年 | 9.3 | 5.6 | 30.2 |
| 築6〜10年 | 13.6 | 7.7 | 32.1 |
| 築11〜15年 | 11.8 | 6.9 | 31.1 |
| 築16〜20年 | 13.9 | 10.2 | 24.8 |
| 築21〜25年 | 11.7 | 10.4 | 20.5 |
| 築26〜30年 | 7.9 | 9.6 | 15.0 |
| 築31〜35年 | 6.9 | 11.5 | 11.0 |
| 築36〜40年 | 7.0 | 10.8 | 11.8 |
| 築41年〜 | 18.0 | 27.3 | 12.0 |
参考資料:REINS TOPIC 築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年) マンション成約物件、築40年超の比率は全体の18%
また、「対新規登録成約率(成約件数/新規登録件数)」は、築6〜10年の物件で32.1%です。
ここから築6〜10年の中古マンション需要の高まりがわかります。
以上の理由から、マンションは築6〜10年が売り時と考えることができそうです。
築11~20年
築11年をすぎるとマンション内に劣化や傷みが生じ、いったん買主がつきにくくなります。
ただし、一回目の大規模修繕を終えた後は外観も設備も新しくなるため、買主が見つかる可能性が高まるでしょう。
大規模修繕の終了後を目指して、計画的に売却準備を進めることがポイントです。
また、管理組合による健全な管理体制や、修繕積立金が適切に運用されているなどの点をアピール材料として活用してください。
築21~30年
マンションの経年劣化があるものの、価格面が手頃なので、買主にとって買いやすい物件です。
二回目の大規模修繕後であれば、さらに買主が見つかりやすくなるでしょう。
表2のデータでは、築21〜30年の成約率は築11〜15年とほぼ同じ11.7%となっています。
築30年以上
マンションの経年劣化により資産価値が下落し、売却価格が下がりやすくなります。
その一方で、リノベーション需要の高まりを反映し、2023年のデータでは築40年超えのマンション売却が全体の18.0%を占めています(表3参照)。
築30年以上の中古マンションの場合、1981年に改正された建築基準法の新耐震基準を満たしていることも重要なポイントです。
1981年以前に建築されているマンションは、新耐震基準を満たしているか確認しておいてください。
マンション売却しやすいベストな期間の見極め方
マンション売却を成功させるためには、マンション購入希望者の心理や市場の動向を把握することが重要です。
売却の成功率を高めるために重要なポイントを解説していきます。
住宅ローン金利が低いときを狙う
マンションを売却するタイミングを考える際、住宅ローン金利の動向を確認することが大切です。
住宅ローンが低いと購入希望者が融資を受けやすくなるため、その結果、売却がスムーズに進む可能性が高いからです。
一方で、日銀の政策金利が上昇すると、連動して住宅ローン金利も上昇します。
これにより買主の金銭的な負担が増え、購入意欲に影響するかもしれません。
実際、2024年3月に日銀はマイナス金利政策を解除し、さらに追加利上げを発表しました。
2025年1月時点で政策金利は0.25%程度に達しており、2025年中も金利が上昇する可能性があります。したがって、日銀の動向を注視する必要があるといえます。
なお、2025年1月時点での住宅ローン金利ですが、「フラット35」の場合、1.970%と低水準(融資率9割超の場合)です。
この低金利状態が続く間にマンションの売却を進めることで、購入希望者が増えることが期待できます。
参考資料:住宅金融支援機構 | 最新の金利情報:長期固定住宅ローン【フラット35】
新機構団信つきの【フラット35】等の借入金利水準より抜粋 2025年1月
大規模修繕が終わってから売却する
マンションの大規模修繕工事が完了した直後は、売却に適したタイミングです。
外観やエントランス、共用部分がキレイに見えるため、内覧者に好印象を与えることができます。
また、外壁塗装や屋上防水工事が行われたマンションは、購入希望者から「管理状態が良い」と高評価を受けやすいでしょう。
マンションの大規模修繕工事は、基本的に「12年周期」で考えられることが多いと言われています。
これは建築基準法による外壁の全面打診調査の義務とも関連しています。
売却を検討している場合、大規模修繕のスケジュールを事前に確認し、終了後の売却を目指して売却計画を立てることがポイントです。
国が公開している相場の指標を確認する
マンションの売却価格を適切に設定するには、公的な相場指標を参考にするのがおすすめです。
不動産市場の状況を客観的に把握できますので、タイミングや市場動向を見据えて、効果的な売却プランを立てましょう。
具体的には、「不動産価格指数」「地価公示」「REINS(レインズ)マーケット情報」を参考にしてみてください。
上記で挙げたサイトは無料で利用可能です。
不動産価格指数
不動産価格指数は国土交通省が公表している指標です。
住宅地やマンションなどの価格動向を地域別や種類別に確認できるので、マンション価格が上昇している時期を逃さないようにしましょう。
特に、新築マンションの価格が上昇している時期は、中古マンションの需要が高まりやすい傾向があります。
参考資料:国土交通省 | 建設産業・不動産業:不動産価格指数
地価公示
地価公示は、国土交通省が毎年公表している、土地の適正な価格を示す指標のことです。
取引を行う際に基準価格として参考にできるだけでなく、土地市場のトレンドを把握するのにも役立ちます。
土地価格と連動してマンション価格が上昇することがあるので、売却のタイミングの判断材料になるでしょう。
一方、土地価格が下落している場合、中古マンションの価格も影響を受けることがあるため、売却は見送ったほうが無難です。
時期によっては希望価格で売却しにくいため、注意が必要です。
REINS(レインズ)マーケット情報
「REINS」とは、不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムのことです。
実際に売買が行われた物件の価格(成約価格)などの取引情報を無料で検索できます。
さらに、実際の取引価格を知ることで、売却価格やタイミングを判断しやすくなります。